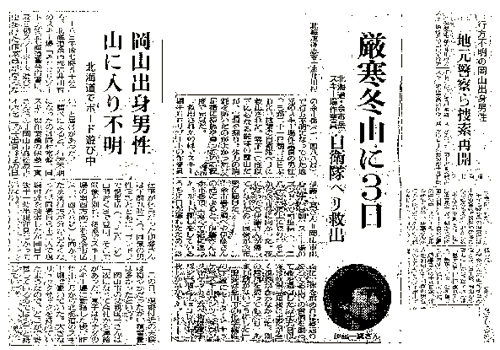
PROROGUE
クレイグ・ケリーの死は、あまりにも僕にとって突然だった。
あれほど山を愛して、あれほど山に尊敬の念を持ち、またあれほど山の知識あるライダーが・・・。
以前、一真はよくこんなことを言っていた。
「自然は人間が考えることよりも、遙かに越えている。」
人間の想像を遥かに越えるもの。それが自然だ。だから、僕たちは歴史から学び未来に向かって歩まないといけないのである。しかし、あろうことか、カナダではあのクレイグの雪崩事故の1週間も経たない間に、まったく同じ地域で雪崩の事故があった。今度の犠牲者はある有名中学の生徒で7人だ。この事故もひじょうに大きい。多くの人は嘆いただろう。
「あの事件の教訓が生かされてはない!」
自然脅威は、まだ人生これからというティーンたちの命を今回も奪ったのである。
これから話すストーリーは、実話である。
僕の友人である伊藤一真が北海道で遭難した話だ。
DAY 1
かねてからスキー場内のあまりにフラットなパウダーに嫌気がさしていた一真は、ルームメイトであり、また山岳系スキーヤーである岡崎ヒロ氏に頼み、余市岳につれていってもらうことにした。ヒロ氏はそれ以前にも、この山はもとより札幌近辺のアウト・バウンドリーを滑り尽くしている、いわばその道のスペシャリスト。そして一真のルームメイトでもあった。北海道にある余市岳は、冬場は8メートルも積もる豪雪地帯。もちろんゲレンデとは違った、いわゆる山岳スキー地域だ。余市岳のピークへは、スキー場からハイクアップして、半日も掛からない予定だ。
2人は、朝イチでリフトから降り、ピークへ向かった。しかし、すでに初めの誤算が、この時から始まっていた。当時、一真の履いていたスノーシューは、面積が狭くて小さいプラスティック製の安物。この日の軽い新雪では、歩くたびに雪面から50センチも沈んでいたのだ。しかも足を抜く時には、雪がスノーシューに乗って重くなる。一方、ヒロ氏はスキーの板の面積が広いために、さほど沈んでいなかった。しかもカカトの浮くバインディングで、スケーティングが楽にでき快適に進んで行く。2人の距離はみるみるうちに広がって行くばかりだった。一真の方はヒロ氏に比べて2分の1以下のスピードだ。これでは、あまりにも迷惑になると思った一真。思わず「上に見えるところに登山者の看板があるから、そこで待ち合わせしましょう。」と提案した。そして、ヒロ氏に先に行ってもらうことにしたのだ。しかし、まさかその提案が大変なことになろうとは、思わなかった。
それから一真は一人でひたすらハイクアップを続けていた。とにかく看板を目指して登ったのだ。気づいてみれば、いつのまにか雪原にいた。山の天気が変わるのは早い。ヒロ氏と別れたときは快晴だったのに、その雪原に着いた頃にはホワイトアウト。つまり一真は、まるで夢の中を彷徨うように、真っ白な世界にいたのだ。そこから、いくらハイクアップを続けても、待ち合わせの場所の看板は、いっこうに現れなかった。「おかしいな」と感じつつもヒロ氏に迷惑をかけまいという思い、必死に看板を探し続けた。しかし、ついに自分はどこに向かうべきなのか、それよりもどこにいるのかも、わからなくなってしまった。コンパスを見たが、針は思っている方向と180度違う方向を示してしまう。コ ンパスは正しい方向を指すべきものなのに、どうしても信用することができずに悩んだ。視界は10メートルぐらいあったので、どっちが上で、どっちが下かぐらいはわかる。とりあえず高いところに行こうと決心した。高いところに行けば、何か見えるかもしれないし、深い霧がないかもしれないのだ。幸運にも、その途中で晴れて来た。しかも、かすかにスキー場リフトの音、「足かけバーをおろして下さい」という放送が聞こえる。一瞬「しめた!」と思ったが、四方から聞こえてくる。つまり山びこによって小さな音が四方八方に散ってしまって、結局どちらにゲレンデがあるのかわからないのだ。一真は喜びのあと、失望を味わった。失望は焦りにつながり、ついには雪原から自分の思う方向に滑り出してしまった。しかし、100メートルくらい滑ったところで、思いとどまった。この時、一真はパニックに陥った。「どうしよう、とにかく下に向かって滑るべきか、それとも上へ登った方がいいのか!?」体の底からあふれるアドレナリンは、非常事態という警告を出す。そして一真はこの時に、今日中になんとかならない事件だということを確信したのだった。この場合、一真の冷静な判断は素晴らしかった。この時に止まらなければ、ただ山を下りようと考えて、必死に夜中まで歩き回っていたことだろう。なんと言う冷静でいて強い判断だろう、彼は覚悟を決めたのだ。
止まった場所は、40度もあるパウダーの超急斜面だった。一真はそこで普通の人では考えられない行動を始めた。いや、もしかしたらだれでも死の使者が来る気配を感じれば、誰でもこういう行動をとるのかもしれない。なんと、今夜の寝床を確保するべく、板を外しノーズを利用して穴を掘り出したのだ。もちろん今までに、そんなことをしたことはなかったが、本能的に生き残るための行動だった。急斜面とパウダーという条件が幸いし、みるみる横穴は掘れていった。汗を掻くと凍るので、なるべくゆっくり動くという、冷静な判断も持ち合わせていた。もう、このころはパニックも過ぎ去り、ただ掘るしかない、という強い気持ちだった。
装備もないのに凍らないで一晩過ごせるかが、一番の問題だったが、やってみないとわからなかった。何より生きるための選択は1つしかなく、そこで休むしかなかったのだ。掘った穴は、人が横に寝れるぎりぎりぐらいのサイズで、その床にバックパックを敷いた。横穴から雪が入らないように板をフタ代わりに使った。バックパックの背の部分はフォームがあり多少の保温性があった。雪山を過ごすその夜の一真の格好は、かなり着込んで古くなったノースフェイスの上下ダウンジャケット、それに足にはソフトブーツにウール・ソックスというものだった。太ももから足先にかけては、バッ
クパックが敷けないために、雪に触れる格好だ。よくある“寝たら死ぬ”みたいにすぐ眠くなるのかなあ、と思っていたが、寒くて気持ちよく睡魔に誘われるどころではなかった。しかし、今日一日のあまりの疲労感から、いつしか睡魔が訪れたようだ。
DAY 2
板の隙間から射す光りで、「生きている」とまず思った。と同時に「意外に大丈夫」という自信がついた。昨晩は、疲れがとれる程度軽く眠れたのだ。板の隙間に昨日降り続いた雪が詰まっており、すべて除雪して外に出てみた。残念ながら、まだホワイトアウトしていた。どう行動しようかと悩んだかが、やはり高いところに行くのがいいと思い、登り始めた。昨日は昼から一晩中雪が降っていたらしく、1メートルぐらいも積もっていた。フカフカ雪で、足場を固められない。3歩登って2歩下がるラッセルで、かなりの重労働だ。汗をかかないように気を配り、ゆっくりゆっくり登っていった。途中でスノーシューの片方がなくなってしまったが、そんなことには構わず、もう一方も外してツボ足で登った。その時、今回持ってきたスノーシューはまったく役に立たない品物だったとわかったのだ。昨日の朝に、行動食のつもりで買ったパン1個、チョコ2枚は、この時点でチョコ板半分になっていた。水は1.5リットル持っていた。「食料は3日ぐらいは大丈夫だけど、水は1日3リットルくらいないとヤバイ」という記憶があったので、水の確保をどうしようかと思っていた。頂上に着いたのは、昼くらいだったようだ。一真は時計を忘れて持って行かなかったので、今何時なのか、皆目見当がつかなかった。その頂上は意外に広く、しかも一方がなだらかな斜面になっていて「ここが本当に頂上なのか?」と思わすところだった。杭が打ってあり、『OO登山部OO岳OO岳縦走』というタスキがあった。つまり、余市岳とは違う名が記されてあったのである。それを見た時、一真は思わず愕然とした。「とんでもないところまで来てしまった。」人生で最大のポツネン感を感じた時だった。いつまでもポツネン感を味わっていると、強風のため体力を消耗するので、風の当たらないところまで下ることにした。そして、なんとこの日もまた穴を掘ることにしたのだ。今度は緩やかな斜面なので、まず垂直に掘り下げ、そこから横穴を掘った。昨日よりさらに長時間かかる作業だった。穴に入り、ひたすらじっとして体力を保つようにした。汗でウールのソックスが凍りついたので、予備のソックスに履き替える。グローブのインナーも替えた。ゴーグルのレンズは雪がへばりつき、まったく見えない品物になってしまったが、保湿性があるので常に付けていた。足先は痛くなり、感覚はなくなってきた。凍傷にでもなって指がなくなったら、スノーボードができなくなると思い、ブーツを脱ぎマッサージを行った。手が冷たくなると、その手を体にあてて温めてから、再び始める。足の指先が凍りそうになるたびにそれを繰り返した。
今、何時かはまったくわからない。だけど突然、どうしょうもなしに大便がしたくなった。小の方は横向きに寝ながら、穴の中でしても、すぐ凍りつくので臭いはしない。しかし、大はずっと穴の中に臭いが充満するだろうし、また何より目の前にいる大を想像したくなかった。ボードでフタしている屋根を取ると雪が崩れて、また始めからやり直しで面倒だし・・・。葛藤していた一真だが「やはりウンコは外で」と思い直し、せっかく作ったねぐらを崩して外へでた。外はさっきよりも強風だった。ズボンをおろして、尻丸出しの格好になった。尻を噛みつくぐらいの、マイナス15度ほどの冷たい風が股ぐらを吹き抜けた。その時、以前読んだ植村直巳の小説を思い出した。「植村さんも、エスキモーキャンプで大便したときは、こんな気持ちだったんだな。」終わった後、すぐに穴を掘り直し中へ入った。暗くなってきたが、夜は意外と大丈夫ということが、昨日わかっていたので気分は楽だった。震えてきたが、なるべく我慢するようにした。震えるとよけいに体力を使うからだ。一真は、待っているみんなを心配していた、。「今頃、下では大騒ぎになっているだろうなあ、いっしょにいたヒロさん心配しているだろうなあ。」 しかし、一真自身は自分が死ぬ恐れある、ということは一切頭になく楽観的であった。それよりも、これからどうやっていくのが一番助かるか、ということばかり考えていた。考える時間は、たっぷりある。これからの一真は、一番良い作戦を考え、ただ「やる」だけだった。そしてこの作戦とは、この頂上らしいところで、天気が回復するまで待っていることだった。
DAY 3
寝たというよりは、目をつむってじっとしていただけだった。板の隙間は、降った雪で埋まっていた。その隙間が明るかったので、少し崩して空を見た。今日も吹雪だった。毎日こりもせず降り続ける雪に、多少の苛立ちを感じる。だんだん水もなくなってきて、どうしようかと思い、空いたペットボトルの中に雪を入れて溶かすことを試みた。ペットボトルの穴は小さいので、ナイフの上に雪をのせながら少しずつ入れていく。ものすごい労力のわりには、ほんの少しの成果でイライラした。「こんなことをするぐらいなら脱水症状で死んだ方がましだ。」と思いやめた。3日目に入り、さすがの一真も体力も気持ちの面でも落ち込んでいた。遭難してから3日目である。3日もこの寒空の下で過ごしていたのだ。ろくな食べ物も食えずに。思考がネガティブ面に動いたのも当然のことだろう。
何回か空の様子をチェックしながら、「まだ吹雪きかあ。」とうんざりした。
夜になった。どういうわけか、3日はもつという自信があった。しかし一方で、足先は揉んでも体温が回復せず、曲がらなくなってきた。足の指が、ブーツの内にくっついているのがわかった。このまでは凍傷で足の指が使いものなる可能性が高い。もちろんスノーボードなんて夢の夢だ。
浅い眠りに一度ついた。しかし、夜中にだんだん息が苦しくなってきて、完全に目が覚めてしまっ。なんと、屋根にしているボードと雪との隙間が空気穴だったのに完全に埋まってしまっていたのだ。しかたなしに、その隙間に手を突っ込んで、穴を開けようとした。しかし、50センチメートルぐらい、雪が積もっているようだ。横に寝ている状態から、精一杯に手を伸ばしても穴を開けられない。起きて除雪する元気は、もう残されていなかった。あまりの疲労感から、この世に元気という言葉があったなんてことは、とうに忘れていた。この時の一真の脳は、理論とかを考える部分はもう作動されず、ただ本能の部分だけが、かろうじて作動していただけだった。だから、そのまま浅い眠りにつくことにした。穴の中は、とてもとても暗く呼吸と心拍数が異常に低下しているようだった。そして一真は、不思議なくらい自分を客観視するのだった。うつろながらに、時々クリアになる脳でこんなことを考えていた。
「修行僧の苦行後というのは、こんな状態なのだろうか。苦行後に神のお告げがあったとか、幻が見えたというけど、それはただ死そうになっただけじゃないのかなあ。悟るとは死にかけて今の自分の殻がすべてはがれてしまって、つまり本当の自分の中身が見えることなのかなあ。」
そして山の麓では、一真を捜していた自衛隊と警察は、今日で捜索を打ち切るかどうかの議論を行っていた。
幸福の女神と、死の使者が飛び交う忙しい夜は、こうして過ぎていったのである。
DAY 4
強い光りが、瞼を刺激する。今までにない明るさだ。幻が見えるまでいかないうちに、ついに夜が明けた。「しめた!」と思い、隙間に手を入れてみた。しかし、横に寝ている状態からでは、手が届かないところまで雪が積もっている。「アレ?アレ?」と思いながら体を起こし、おもいっきり手を伸ばした。天井から崩れた雪が降ってきた後、真っ青な空が一真を歓迎した。あまりの喜びで体を動かしたかったが、ねぐらの上の雪は相当深くて生き埋めになりそうだった。焦る気持ちを、なんとかなだめながら「ゆっくり、ゆっくり」と自分に言い聞かせ、周りの雪を掘った。表面30センチメートルの雪は、積もりすぎたおかげで氷に変わっていた。また穴自体もひじょうに狭くなっていた。崩した雪を穴の一番奥深く押しやる作業に悪戦苦闘しながら、なんとか肩が出るくらいの大きさに開けた。頭を出してわかったことだが、アゴが雪面と同じ高さにあり、つまり1メートル以上も雪が積もっていた。なんとか這い出て、下を見るとスキー場の駅舎が見える!
「ウォー!」
今までの苦労を吹き飛ばすかのように、一真は叫んだ。地球のすべての生き物が一真の雄たけびを聞けるかのように。北海道の広大な青空に向かって、思いっきり吠えたのだ。オレの声、天にまで届け!
ボードは1メートルぐらい下に埋まって、取り出せなかった。バックパックも穴の底に残したまま駅舎が見える方向へ歩き出した。ボードを持って歩かないと、やけに不安だった。しかし、振り返ってみれば迷った時から、ボードは捨てれば良かったのかもしれない。疲労と戦う一真にとっては、かなり重いものだったのだから。だけど、なぜか捨てることができなかった。今まで気にしたことがなかったが、あらためて自分がスノーボードに惚れ込んでいることを感じた。スノーボードへの思いが強いことを感じたのだ。歩いているところは、表面がクラストしていた。しかも、この辺り一面に樹が埋まっていた。だから雪の状態はスカスカで、一歩進むごとに足の付け根まで埋まってしまう。急激に穴に落ちそうにもなり、危ない状態だ。こんな状況の中で歩くから、なかなか前に進まない。体力はほとんど消耗し、息をするのもつらいぐらいだ。晴れていたが、風は強く気温もさらに低くなっている。穴の中で濡れていた体が、一気にパキパキと凍った。顔面に関しては、ほとんど感覚がない状態だ。唇をカチカチさせながら、ひたすら歩き続けた。遠くに見える駅舎を見ながら、体力が保つかどうか不安になった。しかし、不安なことはあまり考えないように努めた。捜索は、もう打ち切られているだろうから、とにかく死力を振り絞って、意地でも自分の力で脱出するしかないと思った。
駅舎を目指す一真の目に、駅舎よりも遙か遠くに、2つの飛行物体が確認された。その飛行物体が、ヘリと確認できると、一真の心は一気に躍った。すぐにでも叫びたい気持ちだ。2機のヘリはあまりにも遠くにいたので、心の中で「俺はここにいる」と強く念じた。すると1機のヘリが自分の方に向かって来るではないか!「いいぞ、いいぞ、もう少しだ。」そして一真は、ヘリに向かって手を振り始めた。ついにヘリは頭上を通り抜け、Uターンして着陸した。あまりの嬉しさに、胸が熱くなる思いだ。以前映画館で見たあの光景。まさに自分はベトナム帰還兵のようだ。そして、ヘリから2人降りてきた! すると、なお映画の世界にいるような不思議感覚。こんな時に、不謹慎に客観グセが出る自分に反省しながら、疲れた目を1人の方に向けた。それは、見覚えのあるホテルの支配人だ。一真にとってはあまりにも偉すぎて、一度もしゃべったことがない人である。一瞬「なぜ支配人が?」と驚いたがすぐに「支配人まで捜索してくれたのか!」と感激した。支配人は言った。「君の名前は何ですか?」あまりにも突拍子もない質問に、面をくらった。なぜ、こんなことを聞くのだろうと。自分しか遭難した人はいないだろうに、と思ったが、意識がはっきりしているがどうか確かめているんだと気づき、最後の力を振り絞って元気に「伊藤一真です。」と言った。
EPIROGUE 1
「ヘリに乗った時は、良かったな、助かったな、という感じで全身の力が抜けるようでした。」
一真の話を聞いてきて、あらためて僕も良かったな、と思った。きっとこれを読んでくださる方も、そう思ってくれるに違いない。この話を聞いていら僕は、ずっと気になっていた、時計を忘れたことに対して、不注意ではなかったかと咎めた。「確かに、反省しています。山岳スキーするのに、持って行かなかったんですから。でも、逆に無くて良かったかなと思います。だって時間をわっかてたら、ずっとイライラしていたと思いますから。」
一真の助かった要因は、どんなピンチになっても、あくまでプラス思考であるんだ、と感心した。それと、時々でる客観視するクセも役に立っているのかもしれない。とにかく、4日もほとんど雪山にいて助かったんだから、スゴイ奴だなと思った。
「でも、勘違いしないでほしいです。助かったからって、僕はヒーローでも何でもないんですよ。自分一人のために何百人もの方に迷惑をかけました。スキー場の人たち、自衛隊、警察、村役場、病院の人たちみんなです。パートのオバチャンたちは夜僕が帰ってくるかもしれないと思いおにぎりを作ってくれました。友達は自分の仕事を捨ててまで、捜索を手伝ってくれました。捜索してくれた人たちを、僕は無理矢理自分と同じ危険にさらしだしたんです。これほどの暴力ってないです。」
続けて一真はこんなことも言ったのだ。
「山をあまくみるな、とよく言うけど、それは最悪の状況を予測して準備するということです。しかし、想像できなかった、もっと最悪の状態になることがしょっちゅうです。つまり自然は人間が考えることよりも、遙かに越えているということを知ってほしいです。」
EPIROGUE 2
クレイグの件を聞いたまず一真は、まるで信じられない様子だった。
「まさか、クレイグが・・・。」
僕もまったく同じ気持ちだ。あれほど山を知っている人間が、しかもこれだけスノーボード界に献立したライダーがなぜ・・・。
一真は続けて言った。
「本当に神様になったね。」
まったくだ。本当に神様になってしまった。ずっと前からスノーボードを愛している僕たちにとっては、クレイグはまさにヒーロー。そしてあのナチュラルなライディングから感じる印象は、神の領域とも思えた。しかし、僕たちがクレイグに形容していた「神」という言葉は、どこか崇拝の意味を込めながらも、まだまだその存在は近いものでもあった。それは、やはりビデオで何度も見ていた身近なヒーローだからだ。だけど、今回の事故で本当にクレイグは神になってしまったように思えた。つまり、それほど遠くに行ってしまった存在というか・・・。その一方でクレイグの存在はどんどん自分の心を支配するようでもあり、まさに神になったという気持ちが強いのである。
「人間は昔からいろいろコントロールしようとして来たけど、結局のところ自然を計算することはできない。なぜなら、人間は自然の中にいるからだよ。その中で生かされているんだ。」
一真の言葉は自然の驚異を体験したことあるだけに、あの事件から10年経った今でもひじょうに説得力があった。
僕も一真もこれからも機会があればバックカントリーに足を運ぶには違いない。だけど、常に快感の裏には死のリスクがあることを決して忘れないだろう。

伊藤 一真


