
日本のスキー場のリフト券は、世界の主要スノーリゾートと比べると比較的手頃な価格で提供されています。しかし、老朽化した設備や人手不足、高級化する海外リゾートとの価格差など、課題も見えてきます。本コラムでは、日本と海外のリフト券価格を比較し、今後の動向や利用者視点での課題について考察します。
文:岩田 克己 @snowheaven_japan
目次
1. 日本のリフト券価格は世界的に見て「手頃」
■ 日本国内の価格相場
日本の多くのスキー場では、ハイシーズンの1日券が4,000円から6,000円程度で設定されています。一部の大型スキー場やインバウンド需要が高いエリアでは8,000円を超える価格設定も見られますが、それでも多くのスキーヤーやスノーボーダーにとって、比較的アクセスしやすい価格帯です。
■ 海外の価格相場
アメリカやカナダ、ヨーロッパの主要スキーリゾートでは、ピークシーズンの1日券が100ドル(約15,000円)を超えることが一般的です。中には200ドル(約30,000円)以上、さらに40,000円を超えるリゾートも存在します。例えば、アメリカの「パークシティ」や「ベイル」では、ピーク時の1日券が40,000円を超えるケースも報告されています。
2. 価格差の要因
■ 施設規模と運営コスト
海外の巨大なスキーリゾートは、広大な敷地や多数のリフト・ゴンドラ、最新の高速リフト、圧雪技術など、大規模な設備投資と運営コストがかかっています。日本のスキー場は、一部の大型リゾートを除いて比較的小規模な運営形態が多く、その分コストを抑えることができます。
■ 収益構造の違い
海外のリゾートはリフト券の売り上げが収益の大きな柱となっています。特にダイナミックプライシング(需要に応じて価格を変動させる方式)を導入しているところが多く、ピーク時には非常に高額になります。一方、日本のスキー場は、リフト券だけでなくレンタル、レストラン、スクール、宿泊施設など、多様なサービスからの収益で成り立っているケースが多いです。
■ シーズンパスの普及率
海外では「エピックパス」や「アイコンパス」など複数のスキー場で利用できる広域シーズンパスが広く普及しており、早期購入で1日あたりのコストを大幅に抑えることができます。日本のシーズンパスは、特定のスキー場やグループスキー場に限定されることが多く、海外のような広域パスはまだ一般的ではありませんでした。しかし、近年では日本でも複数のスキー場で利用できる共通シーズン券が増えてきています。
3. 今後の動向と考察
■ 価格上昇の兆候
近年、日本でも主要なスキー場を中心にリフト券の価格上昇が見られます。特にインバウンド需要の回復に伴い、ニセコや白馬などの国際的なリゾートでは、より海外の価格設定に近づいていく傾向があります。
■ プレミアム化
一部の高級リゾートでは、高額なリフト券に付加価値(ファーストトラック、専用ラウンジ、プライベートガイドなど)を付けて販売する「プレミアム化」が進んでおり、日本のスキー体験も多様化していく可能性があります。
■ 早期購入割引の重要性
日本でも「早割」シーズン券や1日券の割引販売が盛んに行われています。賢くスキーを楽しむには、これらの割引情報を活用することがますます重要です。
まとめと課題
日本のスキー場のリフト券価格は、世界の主要スノーリゾートと比較して現状では非常に手頃です。これは、ひと昔前の「スキーはお金持ちのスポーツ」から、高度成長にともない日本のスキー文化が気軽に楽しめるレジャーとして発展してきたことや、運営コスト・収益構造の違いによるものです。
しかし、国際的な需要の高まりやリゾートの高級化・多角化に伴い、今後は日本のリフト券価格も上昇する可能性があります。特に海外からの観光客が多いリゾートでは、世界の価格水準に近づく動きが見られます。
日本のスキーヤーやスノーボーダーにとっては、早期購入割引やシーズンパスなどを賢く利用することで、今後もコストを抑えて楽しむことが可能です。
しかし、リフト券の価格を上げても、老朽化した設備や慢性的な人手不足といった根本的な課題が解決されない場合、日本のスノーリゾートは国内外の利用者から厳しい評価を受けることになります。
利用者視点からの懸念
1.「価格に見合わない」という不満
■ インバウンド観光客の視点
- 多くの海外スキーヤーやスノーボーダーは、北米やヨーロッパの高級リゾートの価格水準に慣れています。日本の価格が上昇しても、彼らが求めるのは単に安さだけではありません。
- 「日本の雪質は世界最高だが、リフトが古い」という声は以前からあります。高速リフトが少なく、古いリフトに乗る時間が長いことは滑走効率を著しく低下させます。
- 価格が海外並み、あるいはそれに近づく場合、彼らは「リフト待ちが少なく、設備が最新で効率よく滑れる」というサービスを求めます。老朽化した設備が放置されたままでは、日本がJapowと呼ばれる最高の雪資源を有していても、「この値段ならもっと良いリゾートは世界中にある」と判断され、リピート率の低下につながります。
■ 国内スキーヤーやスノーボーダーの視点
- 以前から日本のスキー場を利用している層は、リフト券が安価であることをメリットとして認識していました。
- 価格が上昇する一方で、リフトの速度やゲレンデ整備状況、レストランのサービスなど「体験の質」が改善されない場合、「値上げは仕方ないが、何が良くなったのか?」という疑問を抱くかもしれません。
- 生活コストが上昇している中で、スノースポーツへの支出が「無駄」と感じられると、客足が遠のく可能性があります。
2. サービス品質の低下と安全性への懸念
■ 人手不足によるサービスの劣化
- 人手不足は、リフト運行管理だけでなく、レストランの営業縮小、ゲレンデ整備の質の低下、救護体制の脆弱化など、多岐にわたる問題を引き起こします。
- ゲレンデの圧雪が不十分だったり、コース管理が行き届かなかったりすると、利用者の満足度が低下するだけでなく事故のリスクも高まります。
- レストランが人手不足で営業時間を短縮したりメニューを絞ったりすると、食事の選択肢が限られ快適な休憩が取れなくなります。
■ 安全な運行への不安
- リフトの老朽化は運行停止や故障のリスクを高めます。また、運行に必要な技術管理者の確保も困難になり、「このリフトは安全なのか?」という根本的な不安を抱かせます。
- 実際に人手不足が原因で一部リフトの運行を休止せざるを得ないケースもあり、利用者の体験価値を損なう結果となります。
3. 日本のスノーリゾートのブランドイメージへの影響
■ 「雪質は良いが設備が遅れている」というイメージの固定化
- 最高のパウダースノーという日本の強みは揺るぎませんが、「ハード(設備)がソフト(雪質)に追いついていない」という印象が国内外に定着する可能性があります。
- SNSで情報が瞬時に拡散される現代では、古いリフトや不十分なサービスに関する不満は、日本のスノーリゾート全体のブランドイメージを傷つけます。
結論
リフト券の価格上昇は、老朽化した設備や人手不足といった課題を解決するための投資として理解される必要があります。しかし、単に価格を上げるだけでは、人々は「価格に見合わない」と感じ、満足度やリピート率が低下する可能性があります。
日本のスノーリゾートが持続可能に成長するためには、価格上昇と同時に「投資」を行い、結果として「質の高い体験」を提供することが鍵です。
具体的には:
- リフトの更新や高速化による利便性と安全性の向上
- デジタル化・自動化による人手不足の補完(自動改札機、オンラインサービス予約など)
- スタッフの待遇改善による質の高い人材の確保と定着
- 顧客サービスの向上(ゲレンデ整備、飲食サービスの質向上)
これらの改善が伴って初めて、価格上昇は正当化され、人々は「この値段なら納得できる」と受け入れることができるでしょう。
●以下は、岩田氏が編集長を務める 『Snow Heaven Japan』デジタルブック です。
国内の魅力あふれるスキー場を、美しい写真とともにわかりやすく紹介しています。次の旅の参考にしたり、移動中に眺めながらゲレンデに思いを馳せたりするのもおすすめです。
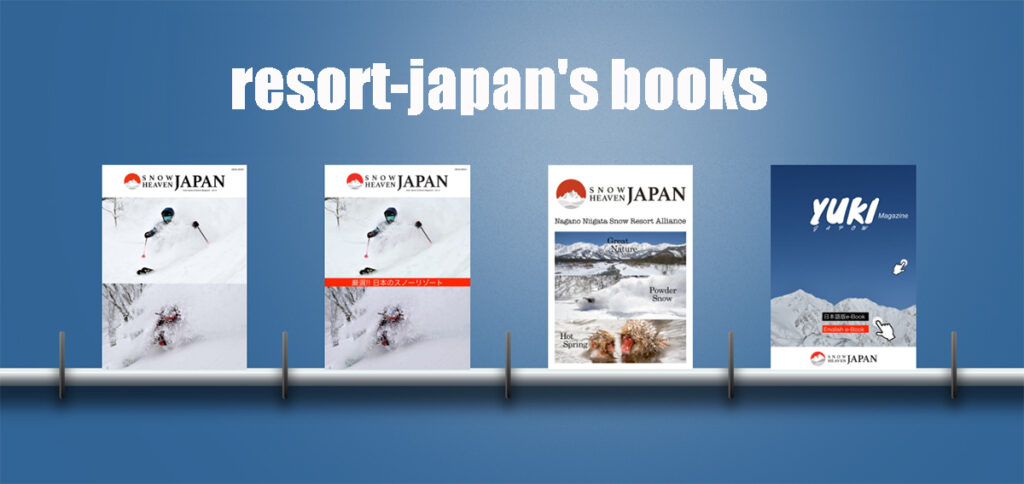

岩田 克己(いわた・かつみ)
(一社)日本スノースポーツ&リゾーツ協議会参与
「Snow Heaven Japan」編集長
(株)トップエンド代表
長年に渡り日本のスノーリゾート地域を取材し、専門誌の発行に携わる。インバウンド向け冊子「Snow Heaven Japan」を創刊するなど、日本のスノーリゾート地域の魅力を国内外に発信し続けている。野沢温泉、蔵王、白馬八方、妙高赤倉、草津のクラシックリゾートの広域連携組織「マウントシックス(Mt.6)」の事務局も務める。近年では、日本のスノーリゾート地域の活性化とウィンタースポーツの振興を加速するため、「一般社団法人日本スノースポーツ&リゾーツ協議会」の設立に尽力。数多くの取材を通じて日本のスノーリゾート地域やウィンタースポーツの事情に精通し、様々な地域、ステークホルダーとネットワークを有する。

